千曲万来余話その517~「ドヴォルジャークの弦楽セレナード作品22からA・ベルクの協奏曲楽器配置まで・・・」
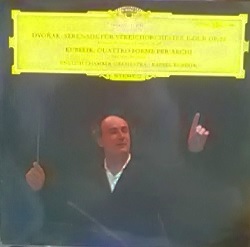 すでに今や弦楽配置でチェロが下手側中央に位置しない演奏は、あり得ないという時代ではなかろうか?クーベリク指揮するイギリス室内管弦楽団の演奏を再生してつくづく、そのように思わされる。
すでに今や弦楽配置でチェロが下手側中央に位置しない演奏は、あり得ないという時代ではなかろうか?クーベリク指揮するイギリス室内管弦楽団の演奏を再生してつくづく、そのように思わされる。
先日キタラホールでアルバン・ベルク1885~1935のヴァイオリン協奏曲の優れた演奏を経験しても違和感をぬぐえず、このような配置だったら違うことだろうと考えた。というのも、その演奏会は現代主流の指揮者左手側にVn、右手側にチェロ、アルトが位置していて上手側奥にコントラバスという、いつも眼にする配置だった。この配置の時、コントラバスを土台と考えたらその向かう延長線は、指揮者の左手側の先、すなわち、合奏体アンサンブルは客席から舞台を前にして左手側に向けられている、つまり正面に向かうことがない横向きの状態と云えるのである。
その前提で管楽器は配置されるという欠点があり、だから、ホルンは下手側配置にされているのだが、本来、ホルンは舞台の上手配置が自然と云うものだろう。ベルという楽器の広がりは指揮者の右手側から見て舞台下手側に容量が大きい方こそ音響が豊かになる。舞台下手側配置ではそれが窮屈だということなのである。
ベルクのVn協奏曲、ある天使の思い出に、という新ウィーン楽派、十二音音楽の傑作はマーラー未亡人アルマの娘マノン19歳の急死へ鎮魂曲レクイエムとして1935年8月に完成、作曲者はその四か月後12/24ウィーンにて、悪性腫瘍で急逝することになる。なにより、調性音楽の土台をしっかり有した、ドデカフォニー十二音音楽であり、後半楽章では、バッハのカンタータ第60番終曲のコラールが引用されている。クラリネットの二重奏が開始されるとき、おお永遠よ汝恐ろしき言葉、1723年作は確信をもって姿を現す。★この夜、指揮者を務めていたハインツ・ホリガーは完全にオーケストラを把握していて、独奏者ヴェロニカ・エーベルレ2006年ザルツブルグ復活祭音楽祭にわずか17歳で登場した南ドイツ・ドナウヴェルト出身の美しい音色は、ホールの聴衆を一気に惹きつける名演奏を繰り広げた。ホリガーは、シューマンの第一交響曲を演奏する当夜のプログラムでも、現代主流の左手側に第一と第二Vnのf字孔をそろえる配置を採用しているのだが、盤友人にとって、あの弦楽配置に違和感をおぼえさせられることわずかに残念である。
当夜の演奏は、音程が完璧に統一されていて揺るぎない演奏、安定感あるハーモニーで演奏されていたのであるけれど、チエロとアルトが中央に配置されていないものでは、中心線が客席からみて左手に向かい、至極残念な結果なのである。ホリガーは、Vnダブルウィングを採用しない演奏家であり、そこのところに限界がある。すなわち合奏の入りを合わせるとき危険性があるというハードルが高い両翼配置を、忌避しているわけである。ところが、ベルクの十二音音楽であっても、ソプラノ、アルト、テノール、バスという四声体のハーモニーは、ボディーをチェロ、アルトという配置に見立てて、左右にヴァイオリンを展開するダブルウィングこそ理想と云えるだろう。
1968年頃録音によるドヴォルジャーク作曲、弦楽オーケストラのためのセレナード、ホ長調作品22クーベリック指揮の演奏は、郷土色豊かで、生命力あふれていて律動的、ハーモニーの美しい音楽に仕上がっている。ここで、第二Vnが指揮者右手側の配置は極めて効果的である。第一楽章モデラート中庸なテンポで、この音楽の終末でテンポを緩めて締めくくる時や、第二楽章ワルツのテンポでの時、合いの手第二Vnの音楽など、作曲家のイメージで第一Vnの奥にはチェロこそ必要で、指揮者の右手側には第二Vnが効果的である。作曲家の指示こそ書かれていないのだが、音楽にしっかり取り組む場合、ヴァイオリン両翼配置というもの、時代の要請として必要十分条件なのではあるまいか・・・
